シニア夫婦に理想的な間取りを紹介|暮らしやすい老後の家づくり

記事
ハウマガ編集部
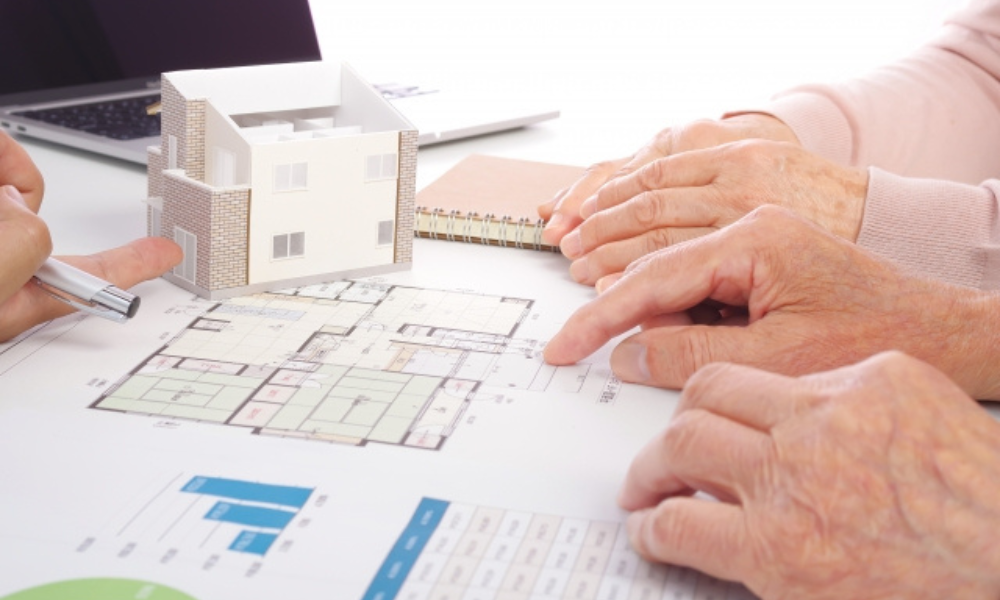
\ Information /シニア夫婦に理想的な間取りを紹介|暮らしやすい老後の家づくり
Contents
子どもが巣立ち、これからは「夫婦ふたりの暮らし」を整える時期。
ふと気づけば、夜間のトイレや冬の脱衣所の寒さ、小さすぎる収納や洗濯動線の遠さが気になっていませんか。
今は元気でも、10年先・20年先も“安心安全”に暮らせる家にしておくことは、将来の医療や介護リスクを減らし、趣味や旅行を楽しむための土台になります。
本記事では、シニア夫婦に最適な間取りを具体例とチェックリストで解説します。
注文住宅で役立つ「暮らしやすい老後の家づくり」の要点をまとめました。
シニア夫婦が暮らしやすい平屋の間取り事例

上下移動のない平屋は、シニア世帯も快適に過ごすことができるでしょう。
段差が解消されるだけでも快適性は向上しますが、バリアフリー機能が増えるだけで、将来も安心して暮らせるはずです。
採光・通風・外時間の確保の工夫が重要なポイントだと思います。
これだけで日々の負担が軽く、将来の介助に役立つでしょう。
次章では、間取り事例から詳しく平屋プランを解説していきます。
間取り事例①:広々空間で快適な4LDK
余白のある平屋を叶えてくれるのが、4LDKほどのサイズ感だと思います。
来客時や将来的に子供夫婦の同居を見据えている方にとって、万能な間取りです。
【間取り工夫】
● 中心設計:LDK約20畳+回遊動線
(例)主寝室→トイレ→洗面
● 採光・通風:南面の大開口+ハイサイドライト、庭・デッキとフラット連携。
● 個室計画:主寝室+趣味室+ゲストルーム+フレキシブル室(将来同居や介助も想定)
● 収納:各室クローゼット+WICで「出しっぱなし」を防止。
● バリアフリー:段差解消・引き戸・手すり計画、車椅子も通れる廊下幅を確保。
● 注意点:広さゆえの冷暖房負荷と音→高断熱・建具配置・ゾーニングで解決。
● ワンポイント:可動間仕切り/将来ベッド2台レイアウト/トイレ幅ゆとり(90cm以上目安)
広さを「管理できる設計」に変えれば、いつでも人を迎えられる安心の住まいになります。
間取り事例②:便利な生活空間を提供する3LDK
3LDKの間取りは〈プライバシー×家事ラク〉のバランスが高いちょうどいい空間を提供します。
中庭型で視線を切りつつ、採光と通風をしっかり取り込めます。
【間取り工夫】
● 型の推し:中庭を囲むコの字/ロの字で外から見えにくい私的外部空間を確保。
● 動線最適化:玄関—洗面—浴室—寝室—WICが一直線/LDK18〜20畳+アイランドで最短家事。
● 居室構成:8.5帖・7帖・6帖の3室(主寝室+趣味/書斎+ゲスト)。
● 温度差対策:断熱強化・床暖・ドアレス洗面でヒートショックの予防。
● 物干し動線:洗面/ランドリー/デッキを一直線に。
● 注意点:中庭は雨仕舞い・防犯・メンテナンス計画を先に固める。
● ワンポイント:来客時は来客動線と生活動線を分離できる建具計画がおすすめ!
動線の交差を抑え、中庭のメンテと防犯を合わせて設計すれば、長く安心して暮らすことができます。
間取り事例③:快適さを追求した2LDK
2LDKの間取りは、〈コンパクト×高機能〉で掃除が楽になるだけでなく、維持費もミニマムにしてくれます。
● 中心設計:LDK16〜18畳の一体空間+回遊キッチン/カウンターで、配膳や片付けを短縮化
● 個室運用:主寝室+フレキシブル室(ゲスト/書斎/趣味)を将来仕切れる下地にすると利便性アップ
● バリアフリー:段差解消・引き戸・トイレ/浴室の近接(介助スペース確保)
● 収納:WIC+可動棚で見せる/隠すを切替、散らからない導線を工夫
● 採光・通風:南窓+ハイサイドで明るさ確保、風の通り道を一直線に。
● ワンポイント:廊下幅1m目安・出入口は引き戸・夜間動線に足元灯
フレキシブル室の仕切りを設置することで、将来的に介助や同居が必要になっても簡単に拡充できます。
小さく建てて賢く整えることで、“生活コストと身体負担を同時に軽く”できる間取りです。
【シニア夫婦】平屋のおすすめポイント

子どもの独立をきっかけに、平屋を検討に加えるケースもあります。
その背景には、階段のない生活がもたらす安全性や、ワンフロアで完結する動線の効率性など、年齢を重ねるにつれて重要度が増す多くの利点があります。
しかし、一方で土地の広さや防犯面など、平屋特有の注意点も存在します。
ここでは、平屋が持つメリットとデメリットの両方を詳しく解説し、シニア夫婦の家づくりにおける判断材料を提供します。
シニア夫婦が平屋を選ぶメリット

シニア夫婦が平屋を選択する理由は、老後の生活を安全かつ快適にするための具体的なメリットに基づいています。
シニア世帯が平屋を選択肢に入れるメリットを紹介します。
修繕費用のコスト削減
平屋は二階建て住宅と比較して、将来の修繕費用を抑えやすいという特徴があります。
主な理由として、外壁の面積が比較的小さく、塗装工事などの際に大掛かりな足場を組む必要がない点が挙げられます。
これにより、足場代だけで数十万円かかる費用を節約できる可能性があります。
また、屋根の形状もシンプルなものが多く、点検や補修が比較的容易に行えます。
老後の生活では、予期せぬ出費は避けたいものです。
建物の維持管理にかかるコストを計画的に低く抑えられることは、経済的な安心につながります。
コンパクトな導線
平屋の魅力の一つは、生活のすべてがワンフロアで完結することによる動線の短さです。
起床してからリビングへ移動し、食事の準備をして、洗濯物を干すといった一連の日常動作が、階段の上り下りなくスムーズに行えます。
特に、掃除や洗濯といった家事においては、水平移動だけで済むため、身体的な負担が大幅に軽減されます。
将来、足腰が弱くなった場合でも、無理なく自立した生活を送りやすい環境を整えられます。
この効率的な動線は、日々の暮らしに時間と心のゆとりをもたらしてくれます。
バリアフリーで安全な暮らし
シニア世代の住まいにおいて、安全性は最も優先すべき項目の一つです。
平屋は構造的にバリアフリー設計と相性が良く、安全な暮らしを実現しやすいといえます。
最大の利点は階段が存在しないことで、家庭内事故で多い転倒・転落のリスクを根本的になくせます。
また、新築時に室内の段差をすべて解消しておけば、つまずきによる怪我の心配もありません。
将来的に車椅子を利用することになった場合でも、廊下の幅や扉の開口部を広く設計しておくことで、大規模なリフォームをすることなくスムーズに対応できます。
シニア夫婦が平屋を選ぶデメリット

多くのメリットがある一方で、平屋にはいくつかのデメリットや注意点も存在します。
これらの点を事前に理解し、対策を検討しておくことが不可欠です。
平屋を選択肢に入れる際の注意点を詳しく見ていきましょう。
広い土地を見つけにくい
平屋は建物を“横に”広げるため、同じ延床面積でも敷地にゆとりが必要になりがちです。
とくにスーパーや病院が近い人気エリアでは、大きめ区画が希少で価格も上がりやすく、希望条件に合う土地が見つかりにくいことがあります。
土地探しを始める前に、建ぺい率・容積率・道路幅・駐車台数などの条件から「建てられる実寸」を把握しましょう。
延床や間口を見直す、準平屋やコンパクトな回遊動線にするなど、予算と立地のバランスを取りながら現実的な解を探すのがおすすめです。
防犯性&遮音性が低い
平屋はすべての部屋が1階に集まるため、窓や出入口が地面に近く、侵入経路になりやすい開口部が増える傾向があります。
道路や隣家が近い場合は、外の音が入りやすい・室内音が漏れやすい心配も。
対策としては、道路側に収納や水回りを配配して音の緩衝帯をつくる工夫も良いでしょう。
防犯性や遮音性を高める対策として、下記の工夫が有効です。
・人感センサー照明
・防犯カメラ
・補助錠
・合わせ(防犯)ガラスの採用
・窓位置の工夫
・塀や植栽で視線をカットする
設計段階から防犯・遮音を前提に計画すると、安心感と静けさを両立できます。
利便性の高い土地が見つかりにくい
シニア世代の暮らしでは、徒歩圏にスーパー・病院・公共交通がある立地が安心です。
しかしそうしたエリアは人気が高く価格も上がりやすい上、平屋に必要な面積の売地がそもそも出にくいという現実があります。
そのため、何を優先するか(利便性/広さ/予算)を夫婦で共有し、優先順位に沿って探すことが大切です。
たとえば「利便性最優先なら延床を少し縮める」「予算重視なら駅距離を緩和する」など、優先順位を明確にしておくと、迷いなく判断できるでしょう。
シニア夫婦の平屋づくりでおさえておきたいこと

平屋は、必要な土地の広さや本体価格の考え方が2階建てと少し違います。
同じ延床なら、基礎と屋根が広くなる分だけ坪単価は平屋のほうがやや高くなりがち。
一方、タイニーハウスは延床20㎡前後・本体価格1,000万円以内がひとつの基準になります。
「いまの暮らしに最適なサイズとコスト感」を起点に、逆算するのが近道になるでしょう。
次章では、住宅費用の相場とタイニーハウスとの違いを具体的に解説します。
住宅費用の目安
老後目前の住まいづくりは、「いまの安心」と「将来の無理のなさ」を同時に満たす資金計画がカギです。
ローン返済や医療リスクも見据えて、平屋をローコスト×高効率で組み立てましょう。
● 予算の基本式を可視化:総予算=本体価格+付帯工事(地盤改良・給排水)+外構+諸費用(登記・税・保険)+家具家電+土地費
● 無理のない返済目安:月返済は手取りの20〜25%を基準に。定年までの完済計画 or 退職後家計の安全余白を確保。
● ローコスト化の設計術:形状は矩形×片流れ屋根で部材・手間を圧縮/面積は“動線の短さ”で稼ぐ(廊下最小、回遊LDK)
● 設備とグレードの考え方:水回りは標準+ポイントアップ(浴室断熱・節湯・食洗機)で“費用対効果”を最大化。
● 収納でコスト最適化:通路兼用の造作収納・可動棚で出しっぱなしを防止
● 見落としやすい費目:照明・カーテン・網戸・物干し金物・外構は坪単価外になりがちなので注意
● 公的制度を活用:自治体の補助金・助成金、省エネ関連制度は早めにチェック。
まずは返済可能額→必要性能→面積・形状の順で決め、見積は本体/付帯工事/外構/諸費用を分けて比較してみましょう。
初期費用は断熱・窓・給湯を優先し、仕上げや造作は後から足せる項目で調整していくと良いでしょう。
タイニーハウスとローコスト住宅の違い
「小さく賢く住む」という点は同じでも、タイニーハウスとローコスト平屋では、違いがあります。
| タイニー | ローコスト平屋 | |
| 規模と法規の前提 | 極小(例:10〜20㎡台)/可動体 用途・建築確認・税率が多様 |
一般的な戸建て基準で申請・常住前提 |
| 暮らし方の想定 | 単身・短期滞在・離れなどミニマル志向 | 夫婦常住×介助・来客を想定 |
| 快適性と余白 | 収納・水回り容量が絞られやすい | 通路幅・手すり・ベッド2台など将来対応の寸法が取りやすい。 |
| 維持費の考え方 | 初期費用を抑えやすい ただ断熱・給湯容量・換気に注意 |
初期の省エネ投資→毎月の光熱費ダウンにつながる |
| 選び方の軸 | 用途(本宅またはサブ)/将来の介助・同居可能性/保管したいモノ量/住み替えの計画性を先に言語化 | |
| ユニバーサル設計 | 段差ゼロ・引き戸・通路幅900mm以上・足元灯、引き出し 回転棚・腰高収納でかがまず取れる |
|
「本宅としての安心」か「最小限の身軽さ」かを先に決め、軸を決めるとスムーズです。
次に①面積 ②収納量 ③将来の介助可否を三点セットで固めれば迷いが少なくなるでしょう。
まとめ

いかがでしたか?
今回は、シニア夫婦にとって快適で機能的な平屋づくりについて、解説しました。
ご夫婦ごとの理想像をベースに、今回の情報を参考にして快適に暮らせる家づくりを楽しんでいただけると幸いです。
シニア夫婦のニーズに応じた間取りや設備が整った平屋は、長い時間を過ごす住まいとして理想的です。
これからの生活に合わせて、ぜひ多様な選択肢を持つ家づくりを検討してみてください。

Today’s Person
山陰の家づくりを全力応援する住まいるマガジンのスタッフ記事です!
次回もお楽しみに!

記事
ハウマガ編集部



